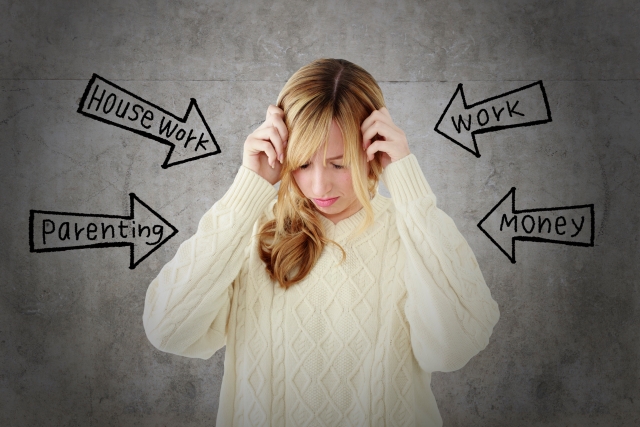・最近ストレスが溜まっている人
・ストレスを上手く発散したい人
スポーツジムの会員様とお話ししていると、会話の中で“ストレス”という言葉をよく聞きます。
「最近ストレスが溜まっているですよ」とか、「ストレスで食べすぎちゃった」などいろんな場面で言われています。
気軽に使う言葉ではありますが、きちんとこの“ストレス”を完全に理解している人はかなり少ないのではないでしょうか。
私は休養学という分野も学んでいますが、体調管理の上で重要な項目であるため、今回はこの“ストレス”をテーマにしていこうと思います。
ストレスの意味や使われるようになった時期は?
このストレスという言葉はいつから使われるようになったのか?
元々“ストレス”という言葉は物理学の用語で”外部からかかる力による物質の歪み”を意味していました。なんとなく分かるような、分からないような・・・といったところでしょうか。
以前カナダのセリエ博士という人がストレス学説というのを1936年に発表した事から、医学の分野でもこの言葉が使われ始めました。医学的いうと、外部からの刺激に対する心や身体の反応の事を“ストレス反応”と呼び、その反応を発生させる刺激の事を“ストレッサー”と呼ばれています。
一般的に言われているストレスはこの両方の意味を含んでいます。
日常生活とストレスとの関係性
ストレスと関係の深い疾病としてうつ病があります。自殺者の多くがうつを伴っていると報告されています。
また、最近では様々な身体症状や疾患と関係する事が分かってきています。
例えば、うつが長い期間続くと脳卒中や心筋梗塞などのにかかりやすくなるという事。その逆で、脳卒中や心筋梗塞になったことをきっかけにしてうつになるという事があります。
また、頭痛、腰痛、めまい等の症状が続いたときに、実はうつが隠れている場合があります。
更に、高齢者等の場合、物忘れが急にひどくなるなど“認知症”のと思われる原因がうつである場合があります。
これらの場合、うつの治療で腰痛や認知症のような状態がよくなる例もあります。
ストレスはない方が良い!は本当か?
「ストレスが無くなったら最高だな」という方が沢山います。しかし、ストレスは本当に悪い事ばかりなのでしょうか?
次のような話があります。ある人がストレス研究者のセリエ博士に「全くストレスのない人はいるんでしょうか?」と尋ねると、博士は「いますよ。よければ、これから会わせてあげましょう。」と答え、近くの墓地に案内しました。そう、ストレスが全くないのは死人だけだと言うのです。
つまり人間にとっては、良いことも悪いこともストレスになるのです。
しかし、同じようなストレスでも自分自身の考え方によって、良いストレスにも悪いストレスにもなります。
例えば、他人から欠点を指摘されたとします。気分が落ち込んでやる気がなくなってしまう人もいますし、欠点を積極的に修正しようとする人もいます。
つまり、ストレスを受ける事で現在の自分を見つめ直したり、新しいことを始めるきっかけになる事もあるのです。
おさらいしましょう。まずストレスとは対人関係であったり、様々な環境・温度・湿度・トレーニング等も全てストレスとなります。精神的なものから物理的なもの、痛みなども全部含んでいます。
日常生活を送るだけでも身体はけっこうなストレスを感じるのです。
ストレスに対抗する方法
ではストレスに身体が対抗していくには、どうすれば良いのでしょうか?
ストレスを受けると、身体は栄養的な面でいうとビタミンCとB群、たんぱく質全般、マグネシウムといったミネラルが失われていきます。つまりストレスを受けると身体の栄養失調が“更に”増えていきます。
なぜ“更に”という表現を使ったかというと、現代人は昔より“カロリー”は増えたと言われていますが、“栄養”は減ったと言われています。慢性的に栄養不足な人が多いのが現代人なのです。
ストレスで多くの栄養素が失われるという事は、栄養価の高いものを摂らなければならない。しかし、大半の方がそれが出来ていなく、間違ったストレス発散方法に走ってしまっています。
具体的には、ストレスの多い時に人は食べ物で言うと塩味、甘味、油を求めがちです。なぜそのような物を求めるかというと、ストレスを感じると血糖値が一時的に下がっていきます。その状態で血糖値が一気に上がると人は多幸感を感じるようになっています。
なので一気に血糖値を上げるようなものを求めるのです。エナジードリンクだったり、ケーキ等の砂糖が入った物などが良い例です。
それは祖先からの名残りで、昔は甘味を摂れる機会が少なく、甘味があると見るだけで食欲がわき、いわゆる別腹のような機能が働き、一気にため込んで血糖値を一気に上げ、幸福感を得ようとするような本能が備わっています。
そのように身体は、塩味、甘味、油のような身体に刺激が入る食べ物を欲するのです。
しかしそのような物を食べると・・・
①体内の消化酵素を大量に使う
②内臓が疲労する
③副腎疲労が起きる
結果・・・もっと疲れます(笑)。
つまりストレスは悪化します。大半の方はこの悪循環を繰り返しています。
ストレスがたまって、塩味、甘味、油を求めている時こそ、健康食を食べる事がとても重要になります。
翌日にストレスを残さない為には、多くの方がやりがちな、ケーキを食べる事でも、ラーメンを食べる事でも、とんかつを食べる事でもなく、オーガニックな健康食を食べる事が一番重要なのです。
普段から健康的な食事を摂っている人や、ファスティング(断食)明けなどでは、人工甘味料などを食べるとものすごくまずく感じます。つまり味覚が正常だとそのような状態になります。
しかし残念ながらそのような状態にある人が少ないので、健康食が一番良いと言っても、それを食べようと思わないのです。そこの改善が一番大変かと思います。
ストレスが多い時の体の状態は?
ストレスを多く感じると身体の中では、コルチゾールやアドレナリン、ノルアドレナリンが過剰分泌されます。いわゆる副腎皮質ホルモンで、トレーニングとも大きく関係があるホルモンでもあります。
ストレスを受けたり、トレーニングをしたりすると、先述のように血糖値はどんどん下がってきます。その下がった血糖値を上げようと、これらのホルモンは働きます。
アドレナリンは有名なので何となくイメージ出来るかと思いますが、これらのホルモンは交感神経優位(活動的優位)に働きます。それによりテンションを保ちストレスに抵抗しようとします。
では、これらのホルモンが過剰に出るとどうなるの?という話ですが、これらのホルモンが血糖値を上げる為に身体の中では、筋グリコーゲン(筋肉にため込んでいる糖)の消費や、筋肉のたんぱく質を分解して糖を生み出すことになります(糖新生)。
それにより筋肉量は減少していきます、つまりボディメイクやダイエットに、勿論健康的にも確実にマイナスになります。
“ストレスはダイエットの天敵”とよく言いますが、科学的にはそのような事が起きています。
トレーニングをする際、交感神経優位にならなければ、そもそもトレーニングができないですし、重要なものではあるのですが、過剰分泌するとよくない・・という事になります。
これは、いつもBCAAやプロテインばかり飲んだり(BCAAは副交感神経⇓交感神経優位になるよう働く)、毎日一生懸命トレーニングしているのに全然休息を取らない、というような事をしていると、ホルモン過多になり、身体にはマイナスに働く為、なるべく避けなければなりません。
過剰分泌されるホルモン
●コルチゾール・アドレナリン・ノルアドレナリン
※ホルモンの話は一般の方にはあまり馴染みがないと思うので、少し難しかったかもしれません。
具体的な改善方法(栄養学観点からの)
では、今度はストレスに対する解決方法を話していきます。
人やラットでの多くの研究では、ビタミンCを投与する事により、体内のストレスレベルが減少したというデータがあります。
ビタミンCやマグネシウムはコルチゾールを分解し適切に作用させる重要な栄養素なので、これらの摂取はとても重要です。
ストレスが過剰でうつ傾向にあるような場合には、加えて葉酸やビタミンB6等の摂取も重要となってくるでしょう。
必要な栄養素
●ビタミンC・マグネシウム
●葉酸・ビタミンB6等(うつ傾向な人はプラスで)
ストレスが回避出来ないとどうなる?
では最後に、これらのストレスが回避出来ないとどうなるのか?有名なラットでの実験があります。
まず小さな箱にいくつかのエリアを分け、一定のエリアにだけ電気を流していきます。当然ラットはものすごいストレスを感じ、コルチゾールを大量に出し続けながら逃げまわります。その途中で電気が流れていないエリアに入り、学習をします。
2回目以降は電気が流れると、その電気の流れていないエリアに逃げるようになります。それを繰り返した後、全面に電気を流します。最初はいつもの流れていないエリアに駆け込みますが、そこも電気が流れてるので、また逃げまわります。
しかし、全ての場所に電気が流れていて、もうどうしようもない状況だという事を把握すると最後は動かなくなります。これは逃げ場のない状況だと諦めた状態になり、コルチゾールの分泌もなくなります。
この状態が人間でいうと、うつの症状になります。
最初は職場環境や人間関係などのストレスにおいて、コルチゾールを出して情緒を保とうとします。そして自然と回避行動をとろうとします。会社を休む、友人と連絡を取る、会社を変える、人付き合いをやめる等、様々な行動を起こそうとします。
しかし、もうどうにもならない状況まで追い込まれると、人は考えるのをやめます。コルチゾールの分泌も止まります。これがいわゆる、うつの重篤な状態です。
こういうことに理解がないと、根性がないとか気合が足りないとか、いわゆる精神論を持ち出しがちになりますが、それは非常に危険です。しっかりと理解していく必要があります。
そこまで重篤な状態にならないようにするには、その前に出るサインを見抜くことが重要です。
会社や学校を休む・サボる。遅刻などもそうです。本人は起きようとしてるのに、なぜかなかなか起きられない、というような状態になります。
そのことを怒るのではなく、ストレスのサインかもしれないと見抜いてあげることです。
私は多くの人数を指導の為カウンセリングしてきましたが、軽いうつ状態にある方は皆さんが思っているよりもはるかに多く、その大半の方は自覚していないのです。
そして、私自身もとても忙しく、上からのプレッシャーが多い状態だった時、思えば軽いうつ状態になっていたと今になって思う事があります。実際なっている時は自分では分からないのです。
何かとストレスの溜まりやすい現代ではありますが、上記を理解し上手にストレスと付き合っていく事が重要です。この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。